こんにちは。医師ママのめぇです。
毎朝使っている電気ケトル。軽くて、すぐにお湯が沸いて、とても便利ですよね。
でも、この便利さが実は危険なんです。
2010年頃から、電気ケトルの転倒による乳幼児のやけど事故が多発しています。2023年現在でも、同じような事故が後を絶ちません。
子どものやけどは大人より深刻
子どもの皮膚は大人より薄いため、熱湯がかかると傷が深く広範囲になります。
重症のやけどは:
- 治療が長期化する
- 高額な医療費がかかる
- 後遺症が残る可能性がある
 めぇ
めぇ「うちは大丈夫」と思わず、今すぐ対策を始めましょう!
なぜ電気ケトルは危ないのか?5つの理由
1. 大量の熱湯が一気にこぼれる
電気ポットと違い、倒れたときの「漏れ防止機能」がない製品が多いです。転倒すると、中の熱湯が全部流れ出ます。
2. 危険な場所に置きやすい
軽くてコンパクトだから、つい置いてしまう場所:
- 床の上
- 低い棚
- テーブルの端
- キッチンカウンターの手前
すべて、子どもの手が届く危険な場所です。
3. 最も危ないのは生後8か月〜1歳
つかまり立ちやハイハイを始めた頃が最も危険です。
- 手に触れるものすべてに興味を持つ
- 軽いケトルを引っ張ってしまう
- バランスを崩して倒す
4. 電気コードに引っかかる
子どもがコードに足を引っかけて、ケトルを倒してしまうケースが多発しています。
5. 「いつもと違う」ときが危ない
事故が起きるのは:
- 朝の忙しい時間
- 来客があって配置が違う
- 掃除で一時的に移動
- ほんの少し目を離した隙
「普段は気を付けていたのに」——ということも多いです。
【実際の事故事例】10か月の男の子の場合
ある朝、お母さんはお弁当作りと朝食の準備で忙しくしていました。
キッチンに場所がなく、いつもは高い場所に置いているケトルを、その日だけ居間の床に置きました。
10か月の男の子は、3歳のお兄ちゃんと一緒にハイハイで遊んでいました。
突然、激しく泣く声。
駆けつけると、倒れたケトルから熱湯があふれ、その中に我が子がいました。
結果:両腕、首、お腹に水ぶくれを伴う第2度熱傷。長期の治療が必要になりました。
お母さんは「いつもは高い場所に置いているのに、忙しい時間にほんの少し目を離した隙の出来事だった」と話しています。
※参考:injury alert より



「たまたま、床の上に置いて」とか「普段は気を付けていたのに」というケースは結構あるようです。
今すぐできる!3つの予防策
対策1:絶対に手が届かない場所に置く
子どもの手が届く高さの目安は、以下の通りです。



成長によって、背の高さだけじゃなくて、腕の長さも変わります。
| 年齢 | 手が届く範囲=台の高さ+奥行き |
| 1歳児 | 約90㎝ |
| 2歳児 | 約110㎝ |
| 3歳児 | 約120㎝ |
子どもの手が届く範囲は、台の高さと奥行きをたした長さで、1歳児は約90cm、2歳児は約110cm、3歳児は約120cmです。これを目安に、高く奥行きがある場所に置く必要があります。
また、コードに足をひっかけてケトルを倒すケースもあるので、高い位置にあるコンセントにつなぐことも必要です。



我が家でも、ケトルの置き場所を見直しました。次男が一歳半だったので、110センチまで届くと過程してみました。




いつもの場所だと、一歳半の子の手が届く可能性があったので、新たな置き場へと移動しました。
対策2:安全機能付きのケトルに買い替える
買い替えるなら、以下の機能があるものを選びましょう。
必須機能
・本体が熱くなりにくい素材のケトルを選ぶ
・転倒湯漏れ防止機能(倒れてもお湯がこぼれにくい)
・蒸気レス設計(蒸気でのやけど防止)
選び方のポイント
Sマーク認証(電気製品認証協議会)を取得している製品なら、安全基準をクリアしています。
Sマーク認証付き おすすめケトル3選
湯漏れ防止機能、蒸気が少ない、Sマーク認証付きの3点をクリアしているのはこれらのケトルです。



安全機能が付いたケトルと、置き場所の工夫で、安全を高めましょう!
対策3:家族全員でルールを共有
- お父さん
- おじいちゃん、おばあちゃん
- 上のお子さん
全員が電気ケトルの危険性を理解し、「絶対に低い場所に置かない」というルールを守りましょう。
もしやけどをしてしまったら
すぐに冷やす
服の上から流水で10分以上冷やします。
- 服は脱がさない(皮膚が剥がれる恐れ)
- 氷を直接当てない(凍傷の恐れ)
すぐに救急車を呼ぶケース
- 広い範囲のやけど
- 顔のやけど
- 手のひら以上の水ぶくれ
必ず病院を受診するケース
- 水ぶくれができている
- 痛みが強い
- 少しでも心配
子どもの皮膚は薄く重症化しやすいので、迷ったら受診してください。
参考になるサイト:教えて!ドクター「やけど受診めやす」https://oshiete-dr.net/pdf/20210125meyasu_yakedo.pdf
まとめ:「環境」で守る
親は常に子どもを見ていられません。
だから、「気を付ける」だけでは不十分です。
「環境」で安全を守る——これが事故予防の基本であり、育児をすこしでも楽しくする方法ではないかと思います。
今日やること
- 電気ケトルを子どもの手が届かない場所に移動する
- コードが垂れていないか確認する
- 安全機能付きケトルへの買い替えを検討する
一緒に「ふわりと包む、家族の安全」を守りましょう♪






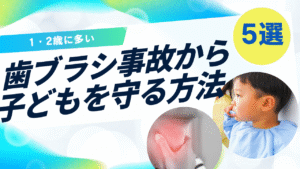

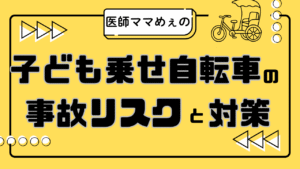
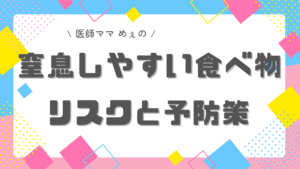
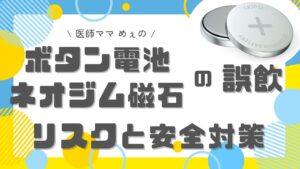
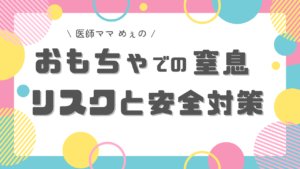
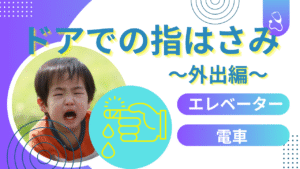
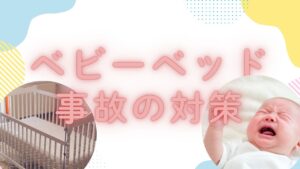
コメント