こんにちは。めぇです。
皆さんは、お酒を飲みますか?自分は飲まないけれど、家族で飲む人はいませんか?
普段飲まなくても、年末年始や親戚の集まり、来客があったとき、家族で食事に出かけた時など…。お酒を飲む機会があると、子どものアルコール誤飲のリスクも高まります。
実は、子どもは大人の10分の1以下のアルコール量でも急性アルコール中毒を起こす可能性があるんです。
今日は、子どものアルコール誤飲の危険性と、今すぐできる予防策についてお話します。
子どもにとってアルコールはどれほど危険なのか
大人とは全く違う、子どもの体
子どもの体は大人のミニチュア版ではありません。
アルコールを分解する肝臓の機能が未熟なため、少量のアルコールでも体内に長時間留まり、重篤な症状を引き起こします。
具体的にどのくらい危険?
例えば、4歳の子ども(体重16kg)がアルコール度数1.5%のゼリーを1個食べただけで、急性アルコール中毒の症状が出た事例があります。
これは純アルコール換算で約1.2gとなり、アルコール度数5%のビールでは、わずか30mL(大ジョッキの10分の1程度)に相当します。
 めぇ
めぇ「そんな少量で?」と驚かれるかもしれませんが、子どもにとってはそれだけで危険なんです。
子どもの急性アルコール中毒の報告数
アルコール誤飲は比較的多く発生しています。日本中毒情報センターの報告によると、2005年~2007年の間に5歳以下の飲料用アルコールの誤飲は年間132件から169件となっています。
• 年齢別では、1歳児が約6割、0歳児が約2割を占めています。
• 5歳以上の子どもでは、フルーツ風味のアルコール飲料をジュースと間違えて飲むケースが多く、この問題については国民生活センターが1994年以降、企業に警告を出していますが、同様の事故が依然として発生しています



缶チューハイなどは、大人でも、ジュースと見間違えそうになるものもありますね。
急性アルコール中毒の症状
血中アルコール濃度によって、以下のような症状が現れます:
| 血中アルコール濃度 | 主な症状 |
| 20~50 mg/dL | 協調運動の低下 |
| 50~100 mg/dL | 判断力・協調性の低下 |
| 100~150 mg/dL | 歩行・バランスの障害 |
| 150~250 mg/dL | 介助なしでの座位保持が困難 |
| 300 mg/dL以上 | 昏睡状態 |
| 400 mg/dL以上 | 呼吸抑制(生命の危険) |
特に怖いのは「低血糖」
小児の急性アルコール中毒で特に注意が必要なのが、致死的な低血糖です。
血中アルコール濃度が100 mg/dL程度でも、低血糖によって意識障害やけいれんを起こすことがあります。
アルコールが肝臓での糖の生成を阻害するため、特に空腹時や夜間に誤飲した場合は危険性が高まります。


実際に起きているアルコール誤飲事故
実際の事故事例を見ていきましょう。
【事例1】洋酒入りゼリーの誤食
発生状況: 4歳の男児と2歳の男児が、冷蔵庫にあった洋酒入りゼリー(アルコール度数約1.5%)を母親に確認して食べました。母親はゼリーにアルコールが入っていることを認識していませんでした。
5〜10分後: 2歳の男児の顔が赤くなっているのに母親が気づき、ラベルを確認してアルコール入りと発覚。
結果: 急速に医療機関を受診。幸い重症化はしませんでしたが、急性アルコール中毒の疑いと診断されました。
※参考:日本小児科学会 Injury Alert No.141



ゼリーのラベルには小さく「洋酒入り」とだけ書かれていて、一目でアルコール入りとはわからなかったそうです。
【事例2】テーブルに置いてあった缶入りアルコール飲料
発生状況: 食事中、1歳の子どもがマグカップに入れてあったぶどう味の缶入りアルコール飲料(アルコール濃度10%)を約50mL飲んでしまいました。
症状: 保護者が気づいたときには顔が赤く、様子がおかしい状態でした。
結果: 急性アルコール中毒で通院が必要となりました。
※参考:消費者庁 子ども安全メール
【事例3】紙パックの焼酎を自分で開けて
発生状況: 3歳の子どもが、のどが渇いたと言い、テーブルに置いてあった紙パックの焼酎を自分で開けてコップに注ぎ、数口飲んでしまいました。
保護者のコメント: 「注ぐまねをしていたので、飲んではいけないと注意したが、本当に飲むとは思っていなかった」
結果: 翌朝嘔吐したため救急センターを受診。アルコール誤飲で通院が必要となりました。
※参考:消費者庁 子ども安全メール
なぜ子どものアルコール誤飲が起きるのか?
理由1:「まさか」という油断
- 「これくらいなら大丈夫」という思い込み
- 「子どもはお酒の味が嫌いだから飲まない」という誤解
- 「ちょっと目を離しただけ」という瞬間
こんな風に考えてしまうかもしれません。
ですが、子どもは味覚が未発達で、甘い味付けのアルコール飲料や、ジュースのような見た目の飲み物は抵抗なく飲んでしまいます。
理由2:容器の見た目がジュースと似ている
- 紙パックの焼酎→ジュースと見分けがつかない
- 缶入りのチューハイ→炭酸飲料に似ている
- ペットボトル入りのみりん→お茶やジュースと間違える
まだ字が読めない子どもは、容器に書かれた「酒マーク」やアルコール分表示は理解できません。
理由3:アルコール含有食品の存在
お菓子や調味料の中にも、アルコールを含むものがあります:
- 洋酒入りチョコレート
- 洋酒入りゼリー
- リゾットなどの調理済み食品
- みりんや料理酒などの調味料
これらの一部には、アルコール含有の表示義務がない、または表示が小さくてわかりにくいものもあります。



洋酒入りお菓子などは、容量がわかりにくいですよね
理由4:危険な場面は日常の中に
- 年末年始の親戚の集まり
- お花見やバーベキュー
- 夏祭りの帰り道
- 夜、親がお酒を飲みながらリラックスしている時間
いつもより気が緩んでいる時、環境がいつもと違う時に事故は起きやすくなります。
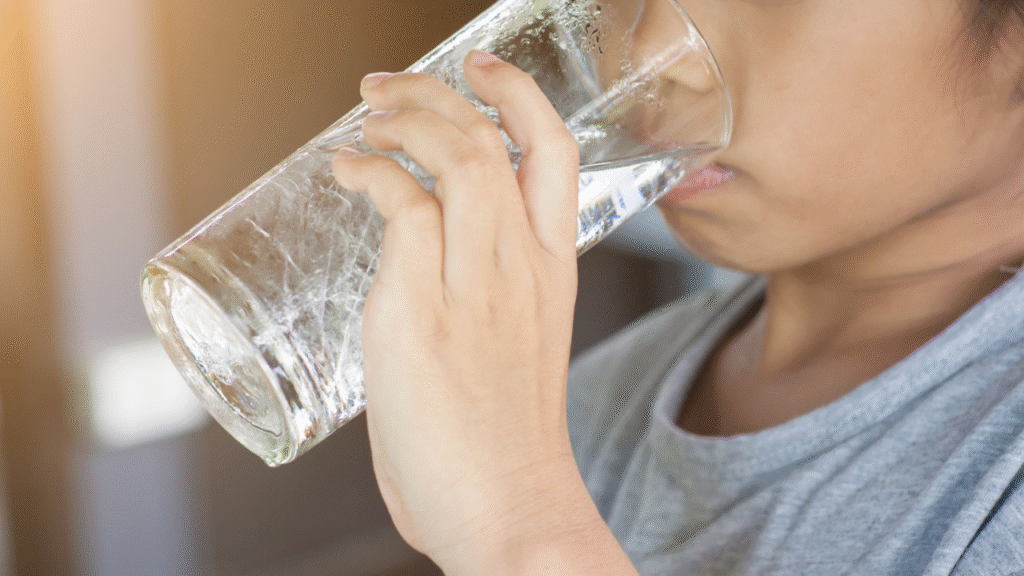
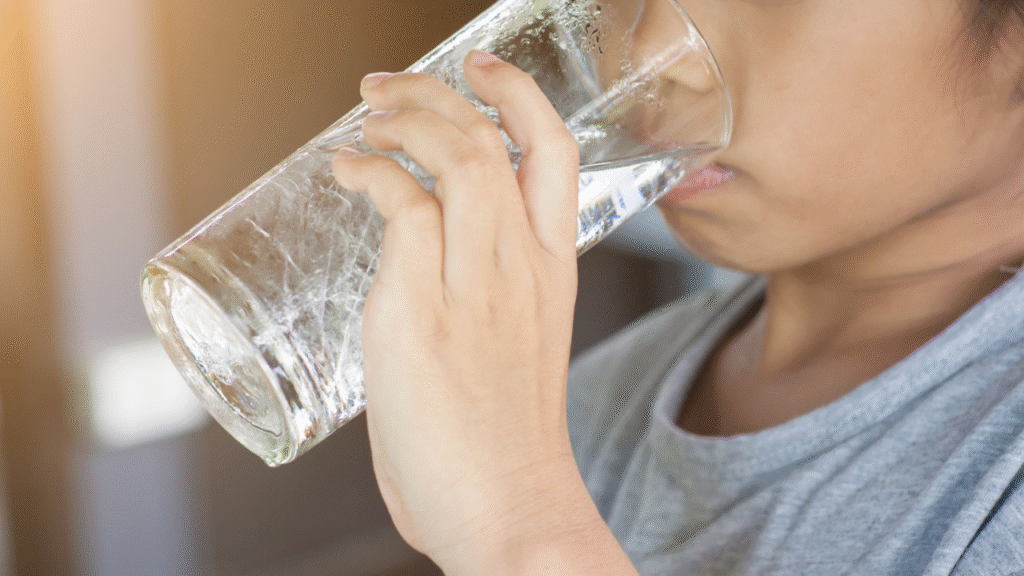
今すぐできる!5つの予防策
大人がアルコールを楽しむためにも、予防策は必要ですね!
対策1:お酒は絶対に子どもの手が届かない場所へ
基本ルール: 子どもの手が届く高さは、台の高さ+奥行きで計算します。
| 年齢 | 手が届く範囲(目安) |
| 1歳 | 約90cm |
| 2歳 | 約110cm |
| 3歳 | 約120cm |
参考:NPO法人 Safety Kids Japan


お酒の保管場所は以下のようなところがおすすめです。
- 冷蔵庫の奥の方、上段にしまう(子どもは踏み台を使って冷蔵庫を開けることも!)
- 高い棚の奥(手前には置かない)
- ロック付きの食器棚
- 子どもが入れない部屋
対策2:飲みかけを絶対に放置しない
我が家でも、大人が飲みかけのお酒のコップを、子どもがのぞき込んでいて、ヒヤッとしたことがあります。
以下のような対策が望ましいです。
- トイレに立つときも持っていく、または高い場所へ
- グラスやカップは使い終わったらすぐに洗う
- 缶やペットボトルは蓋を閉めて、すぐに片付ける
「ちょっとの間だから」という油断が事故を招きます。
対策3:調味料の保管場所も見直す
意外と見落としがちなのが、みりんや料理酒です。
- みりん: アルコール度数約14%
- 料理酒: アルコール度数約13〜14%
ペットボトル入りのみりんは特に要注意です。子どもが簡単に開けられます。
対策:
- キッチンの高い棚へ保管する
- 子どもが入れないように、キッチンにベビーゲートを設置
対策4:アルコール含有食品のチェック
贈答品や頂き物のお菓子は、必ずラベルを確認してから子どもに与えましょう。
チェックポイント:
- 「洋酒入り」「リキュール入り」などの表示
- 原材料欄に「エタノール」「アルコール」の記載
- チョコレート菓子は特に注意(1%以上のアルコール含有表示義務あり)
保管方法:
- アルコール入りのお菓子は、子どもの手が届かない場所に
- または、大人だけで楽しむようにする
対策5:家族全員でルールを共有
アルコール誤飲の予防は、一人だけが気を付けても不十分です。
共有すべき人:
- お父さん、お母さん
- おじいちゃん、おばあちゃん
- 上の子ども(年齢に応じて)
- ベビーシッターさんや、家事代行の方
これらの人と、子どもがアルコールを誤飲する危険性や保管場所のルール、飲みかけを放置しないルールを共有しましょう。



年末年始に帰省するときは普段と環境が違うので、祖父母にも事前に伝えるようにしましょう。
もしアルコールを誤飲してしまったら
アルコールは摂取から血中濃度のピークまで、空腹時で約60分、満腹時で約180分かかります。誤飲直後は症状が軽くても、時間とともに悪化することがあるので、必ず医療機関を受診してください。
すぐにやるべきこと
- 口の中に残っているものを出させる(無理に吐かせない)
- 何をどのくらい飲んだか確認する(容器やラベルを保管)
- 医療機関に連絡・受診する
すぐに救急車を呼ぶケース
- 意識がもうろうとしている
- けいれんを起こしている
- 呼吸が苦しそう
- 顔色が悪い、唇が紫色
- 大量に飲んだ可能性がある
やってはいけないこと
- 無理に吐かせる(気道に入る危険性)
- 水やお茶を大量に飲ませる(アルコールの吸収を早める可能性)
- 様子を見続ける(症状は急に悪化することも)
まとめ:「環境」で守る子どもの安全
子どものアルコール誤飲事故は、「ちょっとした油断」から起きます。
でも、親が24時間ずっと見ていることは不可能です。
だからこそ、「気を付ける」だけでなく、「環境」で守ることが大切なんです。
今日からできること
☑ お酒の保管場所を見直す(子どもの手が届かない高さ・奥行き)
☑ 飲みかけを絶対に放置しないルールを徹底
☑ みりんや料理酒の保管場所もチェック
☑ 贈答品のお菓子はラベルを確認する習慣
☑ 家族全員でルールを共有する
一緒に家族の安全を守っていきましょう!
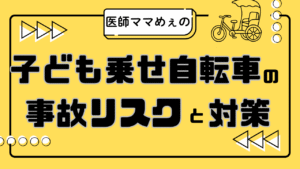
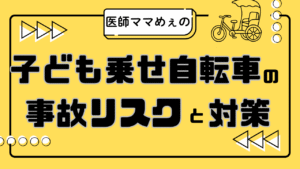


参考資料
- 日本小児科学会 Injury Alert No.141
- 消費者庁 子ども安全メール「子どもの思わぬアルコール摂取に注意!」
- NPO法人 Safety Kids Japan

コメント